EC業界の競争が激化する中、「ec 広告 戦略」で検索する人の多くは、限られた予算の中で“どの広告から始めるべきか”を知りたいと考えています。ネット上には無数の広告手法が存在しますが、実際に成果を上げるためには、自社のフェーズや商材に合ったWeb広告を選び、適切な順序で運用を進めることが欠かせません。
本記事では、ECサイト運営で欠かせない7種類の代表的なWeb広告を取り上げ、それぞれの特徴や目的、効果的な活用法を踏まえながら、どの施策を優先すべきかを解説していきます。単なる広告一覧ではなく、“成果を出すための戦略的視点”で整理しているため、これからEC広告を始める方にも実践的な内容となっています。
ECサイトの集客で活用される主要7種類のWeb広告とは
ECサイトにおけるWeb広告は、ユーザーの購買行動のどの段階を狙うかによって種類と役割が異なります。新規ユーザーの獲得を目的とするものもあれば、既存顧客の再購入を促すリマーケティング型もあります。重要なのは「どのタイミングで、どの広告を打つか」を設計することです。ここでは、ECビジネスで成果を上げるために欠かせない7つの基本広告を順に紹介します。
1. リスティング広告|意欲の高いユーザーを狙い撃ちできる即効性の高い広告
リスティング広告は、GoogleやYahoo!の検索結果に表示されるテキスト広告で、ユーザーが検索したキーワードに連動して配信されます。「通販」「購入」「公式サイト」など明確な購買意図を持つキーワードを狙うため、コンバージョン率(CVR)が高く、短期間で成果を出しやすいのが特徴です。
クリック課金制のため、無駄なインプレッションコストを抑えつつ効率的に集客できる点も魅力です。ECサイトを立ち上げたばかりでブランド認知がまだ低い場合でも、検索経由で確実に購入見込み客へリーチできることから、最初に取り組むべき施策のひとつといえるでしょう。
2. ディスプレイ広告|潜在層への認知拡大とブランド想起を促す
ディスプレイ広告は、ニュースサイトやYouTube、ブログなどに画像・動画付きで表示される視覚的な広告です。購買意欲がまだ高くない潜在層にリーチできるため、ブランドの認知向上や商品の魅力訴求に最適です。
特に、まだ自社ブランドを知らない層に「存在を知ってもらう」段階では欠かせません。リスティング広告が“攻め”の施策だとすれば、ディスプレイ広告は“撒き”の施策。将来的な購入につながる層を育成する長期的な効果が期待できます。
3. ショッピング広告|検索結果に商品画像と価格を表示して購買を直結
Googleショッピング広告は、検索結果の上部に商品の画像・価格・店舗名を直接表示できる広告です。ユーザーが比較検討段階にいる時に視覚的に訴求できるため、ECサイトにとって非常に強力な販売促進ツールです。
価格・在庫・レビューなどの要素を自動的に反映できるため、購入検討中のユーザーを効率よく購買へ導きます。特に物販系ECでは、SEOよりも短期間でトラフィックと売上を伸ばすことが可能です。リスティング広告と組み合わせて運用することで、検索面での露出を最大化できます。
4. リマーケティング広告|離脱ユーザーを再訪問・再購入へと導く再アプローチ施策
リマーケティング広告(またはリターゲティング広告)は、一度自社サイトを訪れたユーザーに再び広告を表示する仕組みです。「カートに入れたけど購入しなかった」「閲覧だけで離脱した」といったユーザーに対して、再度購買を促すことができます。
ECサイトにおいては、初回訪問で購入に至らないケースが大半のため、この広告は非常に高い費用対効果を発揮します。既に商品に興味を持っている層への配信なので、コンバージョン率が高く、広告単価を抑えながら売上を伸ばせる点が魅力です。
5. SNS広告|ブランドの世界観を伝えながら感情的な共感を生む
SNS広告は、Instagram・X(旧Twitter)・Facebook・LINE・TikTokなどのプラットフォーム上で配信される広告です。SNSユーザーは“情報を探している”のではなく、“興味を感じたものに反応する”傾向があるため、ビジュアルやストーリーで訴求できるEC商材と相性が抜群です。
Instagramならビジュアル訴求、TikTokなら動画による体験型訴求、LINEなら再購入やCRM施策と組み合わせるなど、SNSごとに目的を明確に使い分けることが重要です。特に近年は、SNS上でそのまま購入まで完結できる「ソーシャルコマース」も拡大しており、EC戦略の中核に位置づけられています。
6. アフィリエイト広告|第三者の信頼を活かした口コミ型集客
アフィリエイト広告は、ブロガーやメディアが商品を紹介し、購入や申込みが発生した際に報酬を支払う成果報酬型の広告です。企業が直接広告を出すのではなく、第三者を通じて商品の魅力を発信できるため、消費者からの信頼を得やすいのが特徴です。
特に新商品やニッチな商材では、レビュー記事や体験談を通じてリアルな声を届けることで購買意欲を刺激できます。即効性よりも中長期的なSEO効果や認知拡大を狙う施策として有効です。
7. メールマーケティング広告|リピーター育成と顧客単価アップを狙う
メールマーケティングは、新規顧客獲得ではなく既存顧客へのリピート促進に最適な広告手法です。新商品情報やセール案内、ポイントキャンペーンなどを定期的に配信することで、購買頻度を上げ、LTV(顧客生涯価値)を高めることができます。
また、顧客の購入履歴に基づいて内容をパーソナライズすれば、より高い反応率を得られます。SNSやWeb広告に比べてコストが低く、既存の顧客データを最大限に活かせるため、広告費削減と売上拡大を両立できる手段として注目されています。
ECサイト運営においては、これら7つのWeb広告をバランスよく組み合わせることが重要です。最初に購買意欲の高い層へリスティング・ショッピング広告でアプローチし、その後ディスプレイやSNSで認知を広げ、リマーケティングやメール施策で再購入を促す──この一連の流れこそが「成果を出すEC広告戦略」の基本構造です。
広告は単発で考えるのではなく、「顧客の旅路(カスタマージャーニー)」に沿って配置することで、限られた予算でも最大のROI(投資対効果)を実現できます。
① Googleショッピング広告の特徴と効果的な戦略
ECサイトの広告戦略において、Googleショッピング広告は非常に重要な位置を占めています。この広告は、検索結果の上部に商品画像・価格・販売元情報を一覧表示できるフォーマットで、ユーザーが購入を検討している段階に直接リーチできる点が最大の魅力です。たとえば「ワイヤレスイヤホン おすすめ」と検索したユーザーに対して、視覚的に商品比較ができる広告を提示できるため、購入率(CVR)が高い傾向にあります。
また、Googleショッピング広告は従来のテキスト広告よりもクリック率(CTR)が高く、特に価格競争が激しいカテゴリーやブランド指名検索において強い効果を発揮します。ユーザーは価格とビジュアルで直感的に判断できるため、購買意欲の高い層を取り込みやすいのです。
ただし、この広告を成功させるにはデータフィードの最適化が欠かせません。商品タイトルや説明文にキーワードを自然に盛り込み、在庫や価格情報を最新の状態に保つことが重要です。また、同一カテゴリー内で多数の商品を掲載している場合は、ROIを意識した入札戦略や商品グルーピングが成果を大きく左右します。
さらに、P-MAXキャンペーンとの組み合わせにより、AIが自動で広告配信を最適化し、Google全体のネットワーク(検索・YouTube・Gmail・ディスプレイ)に展開できるのも強みです。つまり、Googleショッピング広告は単なる「商品露出」の手段ではなく、ECサイトのデータと連携しながら購買体験を設計する戦略的広告手法なのです。
② リスティング広告の活用と最適な運用方法
リスティング広告(検索連動型広告)は、ユーザーの検索意図に合わせて広告を表示する最もダイレクトな集客手法です。ユーザーが能動的に情報を探している段階で広告を表示できるため、ECサイトにおける高コンバージョン施策として根強い人気を誇ります。たとえば「化粧品 通販 安い」「ランニングシューズ メンズ」など、具体的な購買キーワードを設定することで、商品ページへ直接誘導できます。
ただし、リスティング広告は運用次第で成果が大きく変わるため、「どのプラットフォームを使うか」「誰が運用するか」という判断が戦略の成否を分けます。以下では、代表的なGoogle・Yahoo!の違い、運用体制の選び方、そしてリスティング広告の構造的な限界について解説します。
Google広告とYahoo広告、どちらに出稿すべきか?
GoogleとYahoo!のリスティング広告は似た仕組みを持っていますが、ユーザー層と配信の仕方に違いがあります。Google広告は検索量が圧倒的に多く、幅広い年齢層にリーチできるのが特徴です。特にスマートフォンユーザーが多く、若年層やトレンド感度の高い消費者への訴求に適しています。一方、Yahoo!広告は30〜50代の利用者が多く、日常的にニュースサイトやポータルページを閲覧するビジネス層への訴求に強みがあります。
つまり、若年層向けのECサイトやトレンド商品を扱う場合はGoogleを中心に運用し、社会人向けの商材や定期通販など信頼性重視の商品を展開する場合はYahoo!を補完的に活用するのが効果的です。また、理想は両者を併用し、成果データを比較・分析しながら配信予算を最適化していくことです。特定の媒体に依存せず、ターゲット層に合わせて柔軟に運用方針を変えることが中長期的なROI向上につながります。
自社運用と広告代理店依頼、どちらが成果を出しやすいか?
リスティング広告は、理論上どの企業でも始められますが、運用の質によって効果に大きな差が出ます。自社で運用する場合、費用を抑えながらスピーディーにPDCAを回せるメリットがありますが、広告文のA/Bテスト、キーワードの入札調整、除外設定、分析など多くの作業が必要です。専門知識や経験が不足していると、クリック単価ばかりが上がり、コンバージョンに結びつかないケースも少なくありません。
一方で、広告代理店に依頼すれば専門チームによる戦略設計と運用代行を受けられ、成果を出すまでのスピードが速くなります。特に、月間広告費が一定以上あるECサイトや、複数商品カテゴリを扱う企業にとっては効率的な選択肢です。ただし、代理店に任せきりにすると、データの共有不足や戦略のズレが生じやすいため、定期的なレポーティングと改善会議を行い、自社のKPIと整合性を保つことが重要です。
結論としては、少額予算で始める場合は社内でのテスト運用が適しており、売上拡大フェーズに入った段階で専門代理店との協業に切り替えるのが理想的な流れといえるでしょう。
リスティング広告の限界と効率化の壁
リスティング広告は「顕在層」を狙う上では極めて強力ですが、どれだけ最適化しても効率の限界があります。理由は、検索ボリュームに上限があることと、入札競争によるクリック単価の高騰です。すでに購買意欲の高いユーザーが少ない市場では、同じ層を複数の競合が奪い合う構図になり、広告コストが上昇しやすくなります。
また、リスティング広告は検索キーワードが前提のため、まだ商品に興味を持っていない潜在層にはアプローチしづらいという弱点もあります。そのため、リスティングだけに依存せず、ディスプレイ広告やSNS広告、SEOコンテンツなどを組み合わせた「フルファネル型の広告戦略」が求められます。
さらに、AI自動入札やP-MAXキャンペーンの活用により効率化は進んでいますが、最終的にはデータとクリエイティブの質が成果を決めます。つまり、リスティング広告の真価は単独施策ではなく、「他の広告チャネルとの連携」によって最大化されるのです。
③ ディスプレイ広告(リターゲティング広告を含めた活用戦略)
ECサイトの広告戦略を考えるうえで、ディスプレイ広告は「潜在顧客へのアプローチ」と「離脱ユーザーの再獲得」という2つの目的を同時に果たせる非常に効果的な手段です。検索連動型広告が「今すぐ買いたい」ユーザーにリーチするのに対し、ディスプレイ広告は「まだ検討段階にいる」層にブランドや商品を印象づける役割を持っています。視覚的なクリエイティブを活かして、興味喚起から購買までの流れを自然に導けるのが強みです。特にECサイトでは、ディスプレイ広告を戦略的に活用することで、認知拡大から再訪問促進までを一貫してサポートでき、長期的な売上成長に大きく貢献します。
リターゲティング広告(リマーケティング広告)の仕組みと重要性
ディスプレイ広告の中でも特に成果につながりやすいのが、リターゲティング広告(リマーケティング広告)です。これは一度サイトを訪問したユーザーに対して、他のサイトやSNS上で再度広告を表示する仕組みで、「見込み顧客を逃さない」ための非常に効果的な施策です。たとえば、商品ページまで見たのに購入に至らなかったユーザーに、関連商品や期間限定キャンペーンの広告を表示することで、「もう一度検討しよう」という購買意欲を喚起できます。
ECサイトにおけるリマーケティングの強みは、ユーザー行動データをもとに配信内容を最適化できる点にあります。Google広告やMeta広告(Instagram/Facebook)などでは、閲覧履歴・滞在時間・カート投入状況などをもとにセグメントを細分化し、それぞれに合わせた広告クリエイティブを出し分けることが可能です。これにより、「ただ広告を再表示する」だけでなく、「ユーザーごとに最も響くメッセージを届ける」ことができます。
また、リターゲティング広告は費用対効果が高い点でも注目されています。すでに自社商品に関心を示したユーザーに対して配信するため、クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)が高くなりやすく、無駄な広告費を抑えながら成果を上げられるのが特徴です。特に、購入を迷っている層への「最後のひと押し」として、送料無料キャンペーンや期間限定セールなどを訴求するのは非常に効果的です。
さらに、近年は**動的リマーケティング(ダイナミックリターゲティング)**の導入によって、ユーザーが閲覧した具体的な商品を自動で広告に反映できるようになりました。例えば、ユーザーがECサイトで見たスニーカーや家電製品が、そのままバナーに表示されるといった仕組みです。このパーソナライズされた広告表示は、ユーザーの購買意欲を高め、離脱防止に大きく寄与します。
ただし、リマーケティングを効果的に運用するには、配信頻度や期間の設定にも注意が必要です。あまりに何度も同じ広告を表示すると、ユーザーに「しつこい」と感じさせて逆効果になる可能性があります。適切なフリークエンシーキャップ(表示上限)を設定し、自然な頻度で接触できるよう調整することがポイントです。
また、プライバシー保護の観点から、Cookie制限やトラッキングルールの変更が進む中で、従来のリマーケティング手法だけでは十分な成果が出にくくなっています。そのため、ファーストパーティデータ(自社が収集した顧客データ)を活用し、メールアドレスや会員情報と連携した広告配信を行う「データドリブン型リターゲティング」への移行が今後の主流になると考えられます。
総じて、リマーケティング広告は単なる「再配信の仕組み」ではなく、ユーザー行動に基づいた最適な購買体験を提供する仕組みです。ECサイトの広告戦略全体の中で、検索広告やSNS広告と連携させながら、段階的にユーザーを購買へ導く「リテンション強化施策」として組み込むことで、継続的な成果を生み出すことができます。
④ アフィリエイト広告を活用したEC戦略の実態と注意点
ECサイトの集客施策として近年注目され続けているのが「アフィリエイト広告」です。成果報酬型という特性上、無駄な広告費を抑えながら販売につなげられるため、スタートアップや中小規模のEC事業者にとっても取り入れやすい手法です。実際、ブロガーやインフルエンサーが自社商品を紹介することで、自然な口コミ拡散が期待でき、信頼性の高い購買導線を作り出すことが可能です。
しかし一方で、アフィリエイト広告には他の広告手法にはない独特のリスクや課題も存在します。費用対効果が高いからといって安易に導入すると、思わぬトラブルや無駄なコストを招く可能性もあるため、その特性を理解し、慎重に運用戦略を立てることが重要です。ここでは、EC広告戦略におけるアフィリエイトのデメリットや注意点を詳しく掘り下げていきます。
アフィリエイト広告に潜むリスクと課題とは
アフィリエイト広告の最大の特徴は、成果報酬型であることです。つまり「商品が購入された」「会員登録が完了した」など、事前に設定した成果条件を満たした場合にのみ報酬が発生する仕組みです。そのため、広告主にとっては費用対効果が明確で、リスクを抑えながら集客できるという大きなメリットがあります。
しかしその一方で、この仕組みは“成果を偽装する余地”を生みやすいという課題を抱えています。実際のところ、アフィリエイト広告は他の広告手法に比べて監視体制が複雑であり、不正行為が発生しやすい側面を持っています。
不正CVや不正行為が発生しやすい仕組み
アフィリエイト広告においてしばしば問題となるのが「不正コンバージョン(不正CV)」です。これは、本来成果と見なされるべきでない行為によって報酬を得ようとする悪質なケースを指します。たとえば、自動クリックツールを用いたアクセス水増しや、Cookieを不正に書き換えて他人の成果を横取りする「クッキースタッフィング」などが代表的な例です。
これらの行為は、広告主のコストを無駄にするだけでなく、データの正確性を大きく損ないます。その結果、正しい分析や改善が行えず、広告戦略そのものの方向性を誤るリスクも生じます。特に複数のアフィリエイトパートナーを抱える場合、すべてのトラフィックを監視・精査するのは容易ではなく、管理体制の強化が不可欠です。
さらに、誇張した広告表現や事実と異なるレビューを掲載するアフィリエイターが存在するのも現実です。こうしたケースでは、一時的に売上は上がっても、結果的に顧客満足度が低下し、ブランドイメージを損なうリスクが高まります。信頼を重視するECサイト運営においては、パートナー選定とガイドライン整備が極めて重要なポイントとなります。
運用負担が大きく管理に時間がかかる
もう一つの大きなデメリットは、アフィリエイト広告の運用管理に多大な労力がかかることです。アフィリエイターの数が増えるほど、広告掲載内容のチェックや承認作業、レポート分析、コミュニケーション対応など、日々の運用タスクが膨大になります。
とくに成果報酬型広告は、短期間で成果を評価するのが難しいため、定期的な成果分析とパートナー評価の見直しが欠かせません。また、季節やキャンペーン時期によってアフィリエイターの活動量も変化するため、報酬設定やプロモーション方針を柔軟に調整する必要があります。
そのため、専任の担当者やASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)との連携が重要になりますが、ASP利用にも手数料がかかるため、結果的に想定よりも高コスト化する場合もあります。アフィリエイト広告を「自動的に売上が伸びる仕組み」と誤解するのは危険であり、むしろ継続的なモニタリングと信頼できるパートナーとの関係構築が成果の鍵を握ります。
アフィリエイト広告は、戦略的に運用すればECサイトの売上拡大に大きく貢献する可能性を秘めています。しかし、不正行為のリスクや運用負荷といった現実的な課題を正しく理解し、健全な仕組みづくりを行わなければ、期待する効果を得ることはできません。EC広告戦略においては、アフィリエイトを“低コストで始められる手法”として捉えるのではなく、“信頼と透明性を前提に構築すべきマーケティングチャネル”として位置づけることが、長期的な成果につながる鍵となります。
ECマーケティング戦略におけるメールマガジン広告の活用
ECサイトの広告戦略を考えるうえで、SNS広告やリスティング広告、ディスプレイ広告のような即効性の高い施策に注目が集まりがちですが、実は「メールマガジン広告」も根強い効果を持つ重要な手段の一つです。特にリピーターや既存顧客との関係を深めたい場合、メールマガジンは他のチャネルにはない「パーソナルな接触」が可能であり、購買意欲を直接刺激することができます。企業独自のリストを活用して配信するほか、外部のメールマガジン媒体に広告として掲載する方法もあり、適切に活用すればコンバージョン率を高める効果的な戦略になり得ます。
メールマガジン広告の課題とリスク
しかし、どのような広告手法にもメリットとデメリットが存在するように、メールマガジン広告にも注意すべき点があります。まず第一に挙げられるのは、開封率の低下です。スマートフォンやSNSの普及により、ユーザーがメールを確認する頻度は年々減少傾向にあります。特にECサイトのプロモーションメールは他社と内容が重複しやすく、購読者の関心を引くタイトルやコンテンツを設計できないと、開封されずにスルーされてしまうリスクが高まります。さらに、メール広告を外部媒体に掲載する場合は、配信リストの質にも左右されます。見込み客の属性が合致していない場合、広告の効果は大きく減少します。
また、メール配信においては「タイミングと頻度」も重要な要素です。頻繁すぎる配信は購読解除の原因になり、逆に間隔が空きすぎるとブランドへの関心が薄れる恐れがあります。購買データや行動履歴をもとに最適なタイミングで配信を行う「セグメント配信」や「トリガーメール」を導入することが、効果を維持するための鍵となります。このように、メールマガジン広告は費用対効果が高い一方で、戦略的な設計と継続的な改善が欠かせない手法です。
メーリングリストの管理不備が引き起こすトラブル
メールマガジン広告で最も注意すべきリスクの一つが、メーリングリストの取り扱いミスによる情報事故です。たとえば、配信先のリストに誤ったアドレスが含まれていたり、BCCではなくCCで送信してしまったりすると、個人情報漏えいにつながる深刻なトラブルに発展する可能性があります。特に外部委託先を通じてメール配信を行う場合、顧客情報の取り扱いルールが明確でないと、意図しないデータ流出を招くこともあります。また、古いリストを更新せずに使い続けることで、すでに退会済みや無効なアドレスへ配信してしまうケースも多く、結果としてスパム判定を受けやすくなる点にも注意が必要です。
こうしたトラブルを防ぐには、最新のデータベースを保つこと、顧客の同意を得た上で配信を行う「オプトイン方式」を徹底することが重要です。さらに、配信システムにはエラーメールの自動削除やセキュリティログの監視機能を備えた信頼性の高いツールを選定することが求められます。ECサイトの広告戦略において、メールマガジンは依然として高いROIを誇る手法ですが、情報管理体制の不備がブランド信頼を失墜させかねない点を十分に理解しておく必要があります。
WEB媒体広告を活用したECサイト集客戦略の重要性
ECサイトの広告戦略において、WEB媒体広告(記事広告を含む)は欠かせない集客手法のひとつです。特に自社サイトへのトラフィックを増やしたい場合や、潜在層への認知拡大を狙う際に大きな効果を発揮します。記事広告は、単なる宣伝ではなく「ユーザーにとって有益な情報」を発信しながら自然に商品やサービスを訴求できる点が強みです。読者が抱える課題やニーズに寄り添ったコンテンツを制作することで、信頼感を醸成し、ECサイトへのスムーズな導線を作り出せます。また、メディア媒体によって読者層が異なるため、商材やターゲットに合わせた媒体選定も極めて重要です。たとえば、BtoC商材なら生活情報系メディア、BtoB商材なら業界専門メディアに掲載するなど、広告の“露出先の質”を高めることで、より高い効果が期待できます。さらにSEO対策と掛け合わせることで、記事広告が中長期的な流入源となり、持続的な集客を実現できるのも魅力です。
Facebook広告で狙うECサイトの成果最大化
数あるSNS広告の中でも、Facebook広告はECサイトにとって非常に戦略的な媒体です。Meta社の広告プラットフォームを通じて、FacebookとInstagramの両方に配信できるため、幅広いユーザーにリーチできます。特にFacebook広告は、詳細なターゲティング機能に優れており、年齢・性別・興味関心・行動履歴といった膨大なデータをもとに、精度の高い広告配信が可能です。これにより、無駄な広告費を抑えながら購買意欲の高いユーザーへアプローチできます。また、リターゲティング広告(過去にサイトを訪れたユーザーに再度広告を表示)を活用することで、カゴ落ち対策やリピート促進にも効果を発揮します。さらにFacebook広告では「ダイナミック広告」を利用することで、ユーザーが閲覧した商品や関連アイテムを自動的に表示でき、パーソナライズされた体験を提供できます。加えて、動画やカルーセルなどの多様なフォーマットを組み合わせることで、ブランドの世界観を訴求しつつコンバージョンへと導く広告運用が実現します。特にECサイトの広告戦略全体の中では、Facebook広告を“中間層~顕在層”に向けた導線として設計することで、認知から購入までを一気通貫でつなぐことが可能になります。
ECサイト広告戦略の総まとめ|複合的な設計で成果を最大化する
ECサイトの広告戦略において、単一の媒体や手法に依存するのではなく、複数の広告チャネルを有機的に組み合わせることが成功の鍵です。リスティング広告やディスプレイ広告で顕在層を捉えつつ、記事広告やFacebook広告で潜在層の興味を育てる構成が理想的です。また、SNS広告を通じてブランドの世界観を広げ、最終的に自社サイトで購入に結びつけるという一連の“広告導線”を設計することで、より効率的な成果が得られます。加えて、広告の効果測定と改善も欠かせません。CTR(クリック率)、CVR(コンバージョン率)、CPA(獲得単価)などの指標を定期的に分析し、クリエイティブやターゲティングの精度を高めていくことで、費用対効果を最大限に引き上げられます。
近年では、AIによる自動入札やレコメンド機能の精度も向上しており、データドリブンな広告運用がより現実的になっています。つまり、ECサイトの広告戦略は「出稿」ではなく「最適化」の時代に突入しているのです。どの媒体をどの段階で活用するかを明確にし、ユーザーの購買行動に寄り添った広告設計を行うことが、これからのECマーケティングにおいて最も重要な成功要素と言えるでしょう。

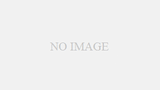
コメント