1. 競合分析とは
ECサイトにおける競合分析とは、自社と同じターゲット層に向けて商品やサービスを販売している他社を調査し、その戦略や成果を客観的に理解する取り組みを指します。競合を把握することは、単なる比較ではなく「自社が市場のどの位置に立っているか」を見極めることでもあります。とくにオンラインショップの世界では、広告の出稿方法、SEOキーワードの設計、SNS運用、顧客レビューの活用など、デジタルならではの施策が成功を左右します。
こうしたデータを継続的に分析することで、市場トレンドの変化を先読みし、価格戦略や販促企画、ブランドポジションの最適化に役立てることができます。競合を理解することは「真似」ではなく「差別化」の第一歩なのです。
2. ECサイトの競合分析でチェックすべきポイント
ECサイトの競合分析を行う際に見るべき項目は多岐にわたります。まず重要なのはサイトの集客力です。検索順位や広告出稿の状況、SNSからの流入比率などを確認することで、どのチャネルが成果を出しているのかを把握できます。次に商品構成と価格帯。売れ筋商品や人気カテゴリ、価格レンジを分析することで、ユーザーが求めている価値や価格感覚が見えてきます。
また、サイトデザインやUI/UXの分析も欠かせません。ページ遷移のしやすさ、カートまでの導線、スマートフォン対応の有無などは、購入率に直結します。さらに、レビュー内容やSNSでの反応も競合分析の重要な要素。顧客がどんな点を評価し、どんな不満を抱えているかを読み取ることで、自社の改善ポイントが明確になります。
3. ECサイトの競合分析の方法
レビュー調査
レビュー分析は、ユーザーのリアルな声を知るための有効な手段です。星評価やコメント内容を丁寧に読み解くことで、他社商品の強みや弱点、顧客満足の源泉を把握できます。ポジティブな意見は「ユーザーが価値を感じる要素」、ネガティブな意見は「改善すべき課題」として、自社の商品開発や訴求に活かせます。
購入調査
実際に競合サイトで商品を購入し、配送スピードや梱包状態、サポート対応を確認する「購入体験分析」も重要です。ユーザー目線での使いやすさや、ブランドの誠実さを見極めることができ、自社のCS改善にも役立ちます。
サイト調査
競合サイトのSEO構造やページ設計、メタディスクリプション、内部リンクの設計などをチェックします。加えて、アクセス解析ツールを活用し、流入キーワードやトラフィック推移を比較すれば、どんな戦略で集客しているのかを明確に掴むことができます。
4. ECサイトの競合分析の流れ
目的を明確化する
まず最初に、何のために競合分析を行うのかを明確にします。市場全体を把握するのか、特定カテゴリのシェアを狙うのか、SEO対策を強化するのかによって、分析の深さと手法が変わります。
ベンチマークとなる競合を選定する
分析対象となる競合企業は、自社と同じ価格帯・顧客層・販売戦略を持つ企業を中心に選ぶことが重要です。規模やブランド力が大きく違いすぎると比較が難しく、実践的な改善策が得られないため注意が必要です。
ツールを活用して分析する
競合の流入経路や広告状況を把握するには、分析ツールの活用が欠かせません。アクセス数の推移、キーワード順位、SNSでのエンゲージメントなどをデータで確認し、感覚ではなく根拠をもって意思決定を行うことができます。
5. ECサイトの競合分析をする際の注意点
競合分析を行う際に陥りやすいのが、データ収集に時間をかけすぎることです。目的を見失い、情報を集めること自体が目的化してしまうと、本来の改善につながりません。また、常に最新情報をアップデートする意識も大切です。EC業界は変化が激しく、数ヶ月前のデータでは実態を反映できない場合もあります。さらに、分析の結果は感覚ではなくデータを根拠に結論づけることが重要。客観的な数字に基づいた判断こそが、マーケティング戦略の信頼性を高めます。
6. ECサイトの競合分析におすすめのツール
SimilarWeb
競合サイトのアクセス数や流入元、ユーザー属性を可視化できる代表的な分析ツールです。無料版でも大まかなトラフィック傾向をつかむことができます。
ユーザーテストExpress
実際のユーザーがサイトを操作する様子を可視化でき、UI/UXの改善ポイントを具体的に発見できます。購買導線の最適化に役立ちます。
イーリサPRO
EC業界特化のリサーチツールで、競合商品の価格変動や販売動向をリアルタイムで追跡できます。仕入れや値付け戦略の参考に最適です。
GRC
検索順位チェックツールとして有名で、指定したキーワードの自社・他社順位を継続的に追えます。SEO戦略の精度を高めるのに役立ちます。
Mailcharts
海外ECを中心に、競合のメールマーケティング内容を分析できるツール。メルマガ設計やクリエイティブの参考になります。
Buzzsumo
SNSやブログで話題になっているコンテンツを可視化でき、トレンドテーマや拡散力の高い投稿を発見するのに適しています。
Alexa(※サービス終了済み)
かつては競合のアクセス状況を比較できる代表的ツールでした。現在は代替としてSimilarWebなどが利用されています。
Facebookオーディエンスインサイト
SNS広告を運用している場合、Facebookのオーディエンスインサイトを使えば、競合ファン層の属性や関心を詳しく分析できます。
競合分析とは
ECサイトにおける競合分析とは、自社のオンラインショップを成長させるために、同じ市場や似た商材を扱う他社サイトの特徴や戦略を調べ、現状の立ち位置を把握するための調査を指します。価格設定、販売方法、集客チャネル、デザイン、SEO対策、SNS運用など、あらゆる観点から競合の強みと弱みを見極め、自社の改善に生かすことが目的です。単なる「他社の観察」ではなく、自社がどう差別化できるか、どう戦うべきかを導くための戦略的な分析といえます。特にECサイト運営ではデータが公開されやすく、ツールを活用することで数値的に比較できるため、定量的なマーケティング判断に直結する重要なステップとなります。
ECサイトの競合分析でチェックすべきポイント
競合サイトの分析を行う際にまず見るべきは「どんなターゲットを想定しているか」という点です。サイトデザインやコピー、扱う商品の価格帯から顧客層を推定し、自社の想定顧客と重なっているかを見極めます。次に重要なのが集客経路です。検索エンジンからの流入が多いのか、SNSや広告による誘導が主なのかを確認することで、競合がどんなマーケティング戦略を取っているかが見えてきます。
さらに、SEO対策の状況や上位表示されているキーワードも注目すべきポイントです。どんな記事やカテゴリページが検索結果で強いのかを分析することで、自社コンテンツの改善指針が得られます。加えて、レビュー数や評価点、リピーター施策、メールマーケティングなど、顧客との接点づくりにどれだけ力を入れているかもチェック対象です。これらを体系的に比較することで、単なる「良し悪し」ではなく「なぜ勝っているのか、なぜ負けているのか」という本質を掴むことができます。
ECサイトの競合分析の方法
競合分析のやり方は、大きく分けて「レビュー調査」「購入調査」「サイト調査」の3つに分類できます。それぞれの手法を組み合わせることで、より実態に近い他社の戦略が見えてきます。
レビュー調査
レビュー調査は、競合サイトの商品ページやモール内の口コミを分析し、顧客が何を評価し、どんな点に不満を感じているかを掴む方法です。星評価の平均値だけでなく、レビューの内容から「配送が早い」「梱包が丁寧」「サイズ感に差がある」などの傾向を読み取ることで、サービス品質やブランドイメージの差が浮かび上がります。ポジティブな意見からは競合の強みを、ネガティブな意見からは自社の差別化チャンスを見出すことができます。特にECサイト運営では「顧客の声=改善のヒント」であり、定性的なデータとして最も価値がある部分です。
購入調査
購入調査は、実際に競合サイトの商品を購入して、購入体験全体を観察するリサーチ手法です。注文から発送、梱包状態、同梱物、フォローメールなど、実際の顧客体験を通して見える情報は、表面的なサイト分析では得られないものです。例えば、到着までの日数や配送業者、カスタマーサポートのレスポンスなどは、顧客満足度を左右する重要な要素です。また、リピート促進のためのメルマガ施策やクーポン配布などのCRM施策を体験することで、競合のリテンション戦略も把握できます。自社のユーザー体験改善に直結する情報を得るために、定期的な購入調査を行うのがおすすめです。
サイト調査
サイト調査は、競合のECサイト全体の設計や導線、SEO施策を俯瞰して分析する方法です。トップページのビジュアル構成、カテゴリ構成、商品ページのレイアウト、カートまでの導線、コンバージョン率を高める工夫などをチェックします。また、SimilarWebなどのツールを使えば、アクセス数やトラフィックの流入経路、滞在時間、離脱率などのデータも把握できます。これにより、どのチャネルが強く、どんなキーワードから流入しているかが明確になります。さらに、競合がどんなキャンペーンを実施しているか、シーズンごとの訴求軸をどのように変えているかなど、マーケティング全体の傾向を掴むこともできます。
ECサイトの競合分析は、単に「他社を真似るための作業」ではありません。市場の構造を理解し、自社の優位性を再定義するための重要な戦略設計です。レビュー調査で顧客の声を拾い、購入調査で実体験を得て、サイト調査で全体像を掴む。この3つの視点を組み合わせることで、数字に裏付けられた実践的な分析が可能になります。
ECサイトの競合分析の流れ
ECサイトの競合分析を行う際は、いきなり他社データを集めるのではなく、まず目的を明確にし、比較対象となる競合を選び、最終的にツールを活用して分析を行うという段階的な流れを踏むことが大切です。単なる情報収集ではなく、「自社の改善や成長のために何を知るべきか」を明確にして進めることで、分析結果が実際の戦略に活かされます。
目的を明確化する
最初のステップは、「何のために競合分析を行うのか」を明確にすることです。自社の売上拡大、SEO順位の向上、広告施策の最適化など、目的によって注目すべきデータや分析方法は変わります。例えば、SEO改善を目的とする場合は検索キーワードや流入経路を重視しますが、コンバージョン率を上げたい場合はUIや購入導線を中心に見る必要があります。目的を具体化することで、分析の方向性が定まり、無駄のないデータ収集が可能になります。
目的が曖昧なまま進めてしまうと、得られた情報が断片的になり、何を改善すべきか分からなくなることが多いです。競合分析の結果を“自社の行動指針”に落とし込むためにも、最初に「なぜやるのか」を明確に言語化しておくことが成功の鍵になります。
ベンチマークとなる競合他社を選定する
次に、比較対象とする競合を選びます。このとき重要なのは、単に業界大手を参考にするのではなく、自社と似たターゲット層や価格帯を持つ「リアルなライバルサイト」を選定することです。直接競合(同じ商材・価格帯)だけでなく、間接競合(異なる商材でも同じニーズを満たすサイト)も視野に入れることで、市場全体の構造がより明確になります。
また、売上規模だけでなく、SNS発信力・レビュー数・ブランドイメージといった非数値的な要素も比較すると、より実践的なインサイトが得られます。たとえば、広告に強い企業とコミュニティづくりに強い企業では戦略が全く異なります。複数の観点からベンチマークを選ぶことで、自社の立ち位置を客観的に把握でき、次に取るべき戦略が見えやすくなります。
ツールを活用して分析する
競合分析を効率的かつ正確に進めるためには、データ取得ツールの活用が欠かせません。たとえば、アクセス数や流入チャネルを把握できる「SimilarWeb」、検索順位の変動を追える「GRC」、広告出稿状況を分析できる「SpyFu」などがあります。これらのツールを組み合わせることで、競合サイトの集客構造や強みを可視化することができます。
さらに、レビュー分析ツールやSNS分析ツールを使えば、顧客の満足度や不満点、トレンドの兆しまで把握可能です。重要なのは、数値だけに注目するのではなく、その背景にある「なぜこの結果になっているのか」を考察することです。ツールから得られるデータをもとに仮説を立て、自社のマーケティングやサイト改善に落とし込むことで、競合分析は単なる調査ではなく、成果を生むための戦略的アクションへと変わります。
ECサイトの競合分析をする際の注意点
競合分析を行う上で最も重要なのは、「一度調べたら終わり」にしないことです。ネットショップの市場は、季節やトレンド、キャンペーン、SNSでのバズなどによって常に変化しています。今日の強みが明日には通用しなくなることも珍しくありません。だからこそ、分析の目的を「競合を評価すること」ではなく、「自社が次に何をすべきかを決めるための材料を集めること」と捉えることが大切です。定点観測の仕組みを整え、定量・定性の両側面から継続的に把握することで、競争優位を保ちながら戦略的に動けるようになります。
定期的に情報をアップデートする
EC市場は変化が早く、数週間でキャンペーンの内容や価格、在庫状況が大きく動きます。そのため、競合調査は一度きりではなく、定期的に更新することが欠かせません。特にセール期や新商品リリース直後など、動きが活発なタイミングは週単位のウォッチが理想的です。日々のモニタリングでは、商品価格、LPの構成、レビュー評価、SNSでの反応数、広告出稿状況などを簡易的にチェックし、月ごとに傾向をまとめることで「どのタイミングでどんな打ち手が成功しているのか」を把握できます。
また、調査結果は都度メモするだけでなく、データベース化して履歴を残しておくと、半年後・1年後の戦略立案に大きく役立ちます。市場変化のスピードに合わせて、自社のアクションも柔軟にアップデートできるようにすることが、持続的な成長の鍵です。
データをもとに結論を出す
見た目の印象や「なんとなく良さそう」という感覚だけで判断するのは危険です。競合のデザインやコピーが魅力的に見えても、それが必ずしも成果に直結しているとは限りません。たとえば、サイトのUIが改善されたことで離脱率が下がったのか、価格変更によって購入率が上がったのかといった「数値で裏付けられる根拠」を重視する必要があります。
GoogleアナリティクスやSimilarWebなどのデータを活用して、訪問数や平均滞在時間、コンバージョン率の変化を比較しながら、「どの施策がユーザー行動を変えたのか」を分析しましょう。さらに、レビュー数やSNS上でのエンゲージメントなど、定量化しづらい部分もできる限り数値化することで、より客観的な判断が可能になります。感覚ではなくデータを基にした結論が、次の戦略の信頼性を高めるのです。
分析作業に時間をかけすぎない
競合分析は奥が深く、やろうと思えばいくらでも掘り下げられます。しかし、分析が目的化してしまうと、肝心の施策実行が遅れてしまいます。大切なのは「完璧な分析」ではなく、「実行に役立つ気づきを短時間で得ること」です。
たとえば、目的を「自社の商品ページ改善」と明確に設定したなら、比較するべきはレビューの構成、カート導線、商品画像の使い方など、テーマに関連する部分だけで十分です。それ以外の情報は次の分析に回すなど、優先順位をつけて調査することが効果的です。
また、時間の上限をあらかじめ設定するのもおすすめです。調査に90分、要点整理に30分、改善提案の作成に30分というようにタイムボックス化すると、無駄な深掘りを防ぎつつスピード感を維持できます。限られた時間の中で「今すぐ活かせる示唆」を抽出することこそ、実践的な競合分析のあるべき姿です。
ECサイトの競合分析におすすめのツール
ECサイトの競合分析を精度高く行うためには、ツールの活用が欠かせません。感覚や印象だけで判断するのではなく、アクセスデータやキーワード順位、SNSでの反応などを客観的に把握することが重要です。ここでは、他社サイトの集客経路や顧客動向を分析する際に役立つ代表的なツールを紹介します。
SimilarWeb
SimilarWebは、競合サイトのアクセスデータを可視化できる代表的な分析ツールです。訪問者数、滞在時間、直帰率、流入経路などを詳細に確認できるため、他社がどのチャネル(検索・広告・SNSなど)に注力しているのかを把握できます。無料版でも十分なデータが得られ、競合サイトの規模感や強みを把握する出発点として最適です。
ユーザーテストExpress
ユーザーテストExpressは、実際のユーザーがサイトを利用する様子をもとに課題を洗い出すユーザビリティ調査ツールです。競合サイトの購入導線や使いやすさを分析することで、自社ECサイトの改善ポイントが明確になります。カート離脱率や購入率を左右する「操作性」や「見やすさ」の比較にも活用できます。
イーリサPRO
イーリサPROは、ECサイト特化型の分析ツールとして高い評価を得ています。競合商品の価格設定、ラインナップ、レビュー内容などを自動で抽出できるため、他社がどのような価格戦略を取っているかが一目で分かります。カテゴリ単位での比較ができるため、自社の商品ポジショニングを考えるうえでも有効です。
GRC
GRCはSEO対策の定番ツールで、自社と競合の検索順位を自動的に追跡できます。特定のキーワードでどのサイトが上位にいるのか、順位変動がどのように起きているのかを可視化できるため、競合のSEO戦略を読み解く手助けになります。コストが低く、導入のしやすさも魅力です。
Mailcharts
Mailchartsは、競合他社のメールマーケティング戦略を分析できる珍しいツールです。配信頻度、件名、デザイン、タイミングなどを比較することで、自社のメール施策改善に役立てられます。特にリピーター施策やカゴ落ちメールを行うECサイトにとって、非常に有効なリサーチ手段です。
Buzzsumo
Buzzsumoは、SNSやWeb上で「どんなコンテンツが話題になっているか」を可視化できるツールです。競合が発信している投稿や記事の中で、ユーザーの反応が大きいものを抽出し、自社のコンテンツ戦略に反映できます。InstagramやX(旧Twitter)などのトレンドを把握する際にも役立ちます。
Alexa
Alexa(サービス終了前まで)は、Webサイト全体のトラフィックランキングを確認できる定番ツールでした。現在はSimilarWebなどが代替的な役割を担っていますが、Alexaのようなトラフィックシェア分析ツールを使うことで、競合サイトの市場ポジションや成長性を把握できます。
Facebookオーディエンスインサイト
Facebookオーディエンスインサイトは、Meta広告(Facebook/Instagram)を活用している企業にとって欠かせない分析ツールです。競合ブランドのフォロワー層や興味関心、地域、年齢構成などを分析でき、広告ターゲティングやクリエイティブ戦略の策定に活用できます。特にECのSNS運用では、顧客のペルソナを精緻に設定するために有効なツールです。
これらのツールを組み合わせて活用することで、数字で見えるデータ(定量分析)と、ユーザー行動から得られるインサイト(定性分析)の両方を網羅できます。競合分析の目的は単に「真似をすること」ではなく、「なぜ選ばれているのか」を理解すること。多面的なデータをもとに、自社の強みを磨く戦略を立てることが、ECサイトの成長につながります。
まとめ
ECサイトの競合分析は、単なる他社の観察にとどまらず、自社の成長戦略を描くための「羅針盤」といえるプロセスです。市場における自社の立ち位置を正確に把握し、顧客ニーズやトレンドの変化を読み解くことで、施策の優先順位や改善点がより明確になります。重要なのは、データを集めること自体が目的ではなく、その情報をどのように意思決定に活かすかという視点です。アクセス数や広告施策、商品ラインナップ、ユーザー体験といった各指標を客観的に比較し、根拠のある打ち手を導き出すことが、継続的な成果につながります。
また、競合分析は一度実施して終わりではなく、季節や市場環境の変化に応じて定期的に見直すことが求められます。特にEC業界ではトレンドの移り変わりが早いため、データを最新化し続けることで、常に戦略を柔軟にアップデートできます。さらに、ツールを活用することで膨大なデータの可視化や比較が容易になり、マーケティングチーム全体での意思共有もスムーズになります。
最終的に、競合サイトの動きを正しく読み解き、自社の強みを再定義できるかどうかが成果の分かれ目です。単なる模倣ではなく、「なぜその施策が効果を生んでいるのか」を深く分析し、自社のブランド価値や顧客体験に落とし込むことが、本当の意味での差別化へとつながるのです。競合を知り、自社を磨く。その継続こそが、ECサイトが長期的に勝ち残るための最も確実な方法といえるでしょう。

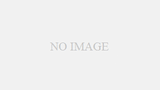
コメント